前回は、各所得控除の 「障がい者控除」「ひとり親控除」「寡婦控除」 「勤労学生控除」 について確認したよね
今回は、その各所得控除の中の「社会保険料控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」 「小規模企業共済等掛金控除」 についてそれぞれ確認していくよ~
⑨社会保険料控除
納税者本人または、生計を一にする配偶者等に係る社会保険料を支払った場合に適用することができる
社会保険料の対象となる主なものは次の通り
健康保険の保険料
国民健康保険の保険料
厚生年金の保険料や厚生年金基金の掛け金
国民年金の保険料や国民年金基金の掛け金
雇用保険の保険料
介護保険の保険料 など
※ 生計を一にする配偶者等が公的年金受給者である場合の公的年金から控除される介護保険料は、納税者本人の社会保険料控除とすることはできない(受給者本人の収入から控除されるべきだから)
⑩生命保険料控除
生命保険料を支払った場合に適用することができる
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料に区分し、各控除額を計算する。
※ 介護医療保険料が平成24年に新設された。それに伴い、他の保険料も旧契約・新契約に分けられて平成23年12月31日以前に契約したものか、平成24年1月1日以降に契約したものかで控除額が異なってくる
※ここは所得税にあわせて住民税の控除額も問われることがあるのでまとめて確認しておこう
所得税の控除額
旧契約(平成23年12月31日以前契約)
| 年間の払込保険料など | 控除額 |
| 25,000円以下 | 払込保険料などの金額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料など×1/2+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 払込保険料など×1/4+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
※ひと区分の保険料等が年額100,000円超の場合が最高となり一律50,000円控除額となる
※2つ区分(一般生命保険料・個人年金保険料)の控除額は、最高100,000円までとなる
新契約 (平成24年1月1日以降契約)
| 年間の払込保険料など | 控除額 |
| 20,000円以下 | 払込保険料などの金額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料など×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料など×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
※ ひと区分の 保険料等が年額80,000円超の場合が最高となり一律40,000円控除額となる
※3つ区分(一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料)の控除額は、最高120,000円までとなる
住民税の控除額
旧契約(平成23年12月31日以前契約)
| 年間の払込保険料など | 控除額 |
| 15,000円以下 | 払込保険料などの金額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | 払込保険料など×1/2+7,500円 |
| 40,000円超 70,000円以下 | 払込保険料など×1/4+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律35,000円 |
※ひと区分の保険料等が年額70,000円超の場合が最高となり一律35,000円控除額となる
※2つ区分(一般生命保険料・個人年金保険料)の控除額は、最高70,000円までとなる
新契約 (平成24年1月1日以降契約)
| 年間の払込保険料など | 控除額 |
| 12,000円以下 | 払込保険料などの金額 |
| 12,000円超 32,000円以下 | 払込保険料など×1/2+6,000円 |
| 32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料など×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
※ ひと区分の 保険料等が年額56,000円超の場合が最高となり一律28,000円控除額となる
※3つ区分(一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料)の控除額は、最高70,000円までとなる
所得税・住民税の控除額(まとめ)

旧契約(所得税)各控除最高5万円 合計最高10万円(住民税)各控除最高3.5万円 合計最高7万円
新契約(所得税)各控除最高4万円 合計最高12万円(住民税)各控除最高2.8万円 合計最高7万円
⑪地震保険料控除
居住用家屋や生活用動産を目的に地震保険料を支払った場合に適用することができる
年間の払込保険料など5万円以下 ・・・ 支払金額全額が控除額
年間の払込保険料など5万円超 ・・・ 一律5万円が控除額
⑫ 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済の掛金や確定拠出年金等の掛金を 支払った場合に適用することができる
今日の活動記録~
今日は、疲れたのでウォーキングは休養しました~~










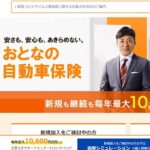
コメント